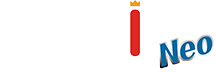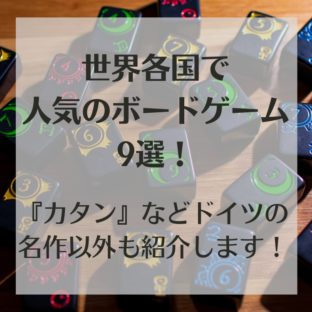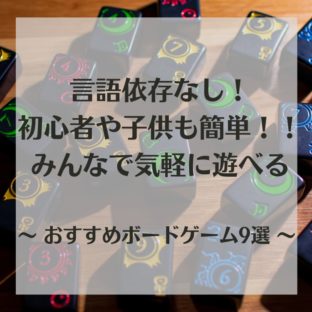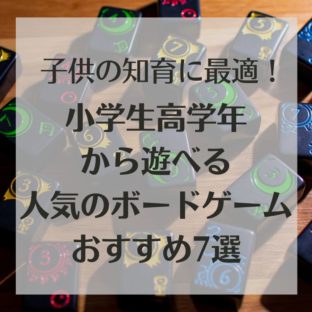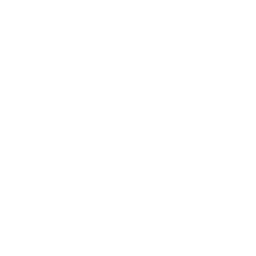言語依存なし!初心者や子供にも簡単なおすすめボードゲーム9選
「ボードゲームって楽しそうだけどなんだか難しそう……」
「ルール説明やカードのテキストをたくさん読むのはちょっと……」
ボードゲームに興味はあるけど、そんな印象があるからどうしても遊ぶ気になれない……。
そういった読者の方へ向けて、本記事を執筆しました。
確かに、ボードゲームの中にはルールが煩雑なものや準備だけで数十分かかるものがあって、初心者にはハードルが高いですよね。
ですが、それを理由にボードゲームを遊ばないのはもったいない!
本記事ではボードゲームの中でも簡単に遊べて、ボードゲームを普段遊ばない初心者でも簡単に熱中できるおすすめのボードゲームを紹介していきます。
ぜひ、最後までお読みいただき、お気に入りのボードゲームを探してくださいね。
初心者が熱中できるおすすめのボードゲームとは?
さて、世の中には日本語化されているもの、されていないものも含めて様々なボードゲームがあります。
この中で、完全なボードゲーム初心者が遊ぶボードゲームとしておすすめなのは、以下の特徴を持つボードゲームだと考えます。
①ルールが簡単である
②準備に時間がかからない
③ゲームで使う内容物の中にテキスト(文章)が多くない
④ある程度の運要素がありなおかつ戦略性も求められる
①~②に関しては分かりやすいと思います。
たとえば手番で8つくらいの選択肢があるボードゲームだと、初心者は手番毎に「何ができるんだっけ……」と混乱しやすいです。
さらに、それだけルール量があると、ルールブックも当然分厚いため、遊ぶまでのハードルがかなり上がります。
多くのボードゲームはデジタルゲームのように「ゲーム内でチュートリアルを挟む」という親切設計ではなく、遊ぶためにはこの分厚いルールブックを読破することが必須となるからです。
また、遊ぶ前のハードルというと準備の長さも大きいでしょう。
準備だけで20分かかる、などと言われると「その間に別のことした方が良くない?」と言われても仕方ありません。
私たちボードゲーマーの感覚がずれているだけで、これが世間的には妥当な反応なんです!

③に関しては遊ぶメンバーによって多少事情が異なります。
例えば普段からTCG(トレーディング・カード・ゲーム)やTRPG(テーブルトーク・ロール・プレイング・ゲーム)などに親しんでいるメンバーですと、テキスト量の多いカードを用いたボードゲームも、簡単に楽しめるはずです。
ですが、普段からそうしたテーブルゲーム全般に馴染みのないメンバーだと、ゲーム内でテキストを読み理解するのに時間がかかり、テンポが悪くなったり、ついていけなくなったりしかねません。
④に関してはメンバーに加えて、どういった目的で遊ぶかにもよりますが、こちらも重要な要素です。
たとえば100%戦略で運が介在しないタイプのボードゲーム(有名なものでは将棋やチェスなど)を遊ぶ場合、どうしてもボードゲームに普段から親しんでいるメンバーが同卓内にいるとその人が有利になりがちです。
逆に運だけで勝負が決まるようなボードゲームだと、瞬間的には盛り上がりますが、どうしてもリプレイ性には欠けるため「楽しかったけどボードゲームってのはこんなもんか」となりかねません。
もし、初心者が「ボードゲームの世界」への第一歩として遊ぶゲームを選ぶなら、適度に運要素と戦略要素が混じったゲームを選ぶと良いでしょう。
前置きが長くなりましたが、ここからは実際に初心者におすすめの簡単で熱中できるボードゲームを紹介していきます。
『レキシオ』

まずは当サイトで取り扱っている『Lexio(レキシオ)』
言語依存はなく、初心者におすすめの簡単なボードゲームです。
『レキシオ』は麻雀牌のようなずっしりとした牌を使って、トランプの『大富豪』のようなゲームを数ラウンド行います。
ただし、役は大富豪と少し違い、トランプの『ポーカー』の役に似ています。
ラウンド終了時に下位のプレイヤーが上位のプレイヤーに対して残り牌数に応じた得点の支払いを行い、決められたラウンド数を終えた時点で最も高得点を稼いだプレイヤーが勝利します。
もちろん各ラウンドの初期牌という運要素はありますが、複数の牌から成る役を崩さずに戦うか、役を崩しながら少しずつでも牌を出すか、という選択を毎手番迫られる戦略性が重要なボードゲームです。
さらにはゲームトータルでどうやって得点を重ねるか、という長期的なプランニングも必要なため、ラウンド毎に初期牌に応じた戦い方を求められます。
腕に自信がついてきたら全国大会、世界大会まである奥深いボードゲームなので、これを機に始めてみてはいかがでしょうか。
レキシオチャンピオンシップ(JLC)についてのレポートはこちら!
『コヨーテ』
『コヨーテ』はブラフとハッタリを交えつつ、場に出た札の合計値を推測する短時間で遊べるボードゲームです。
プレイヤーは1枚ずつの札を公開し、全員の札の合計値を超えないように数字を手番で宣言していきます。
そうして宣言された数字が超えたと思われたら、手番プレイヤーが前の宣言に対して「コヨーテ!」と宣言します。
ただし、各プレイヤーは配られた札を自分だけが見えないように公開する必要があるため、最初は自分の札の数字が分からない状態で、合計値を推測しなければなりません。
「コヨーテ」が宣言されたらすべての札を確認後、合計値を確定。合計値より上の数字が宣言されていたら「コヨーテ」と宣言されたプレイヤーがライフを失い、合計値以下の数字を宣言していた場合は「コヨーテ」を宣言したプレイヤーのライフが減ります。
相手の宣言によって自分の札を推測するのが『コヨーテ』の基本的な戦術ですが、時には他プレイヤーを惑わすためにハッタリで大きめの数字を宣言するのも有効です。
ルールも簡単で短い時間で決着する割に、熱い駆け引きや心理戦が楽しめる、オススメのボードゲームです。ついつい「もう一回」と遊び続けて時間が溶けていくことでしょう。

『ハゲタカのえじき』
『ハゲタカのえじき』は「バッティング系」と呼ばれるジャンルの簡単に遊べるボードゲームです。
プレイヤーは最初に配られた「1」~「15」の手札を毎ラウンド1枚ずつ使い、それぞれのラウンドで公開された「-5」~「-1」の失点札や「+1」~「+10」の得点札を取り合います。
得点(失点)札の取り方は簡単で、得点札は一番数字が大きい手札を出した人、失点札は一番数字が小さい手札を出した人の所に来ます。
それだけ聞くと誰もが「『+10』の時に『15』を出せばいいじゃない」と考えるかもしれませんが、実はこのゲームにはもう一つ重要なルールがあります。
それは、手札から他のプレイヤーと同じ数字を出したプレイヤーは、その得点(失点)札の獲得権利がなくなる、というルールです。
これにより他のプレイヤーが仮に全員「15」を出したとしたら「1」でも「+10」の札を獲得できる可能性がありますし、逆に「1」の札を「-5」の時に出しても、他の人が「1」を出してくれれば失点せずに済むこともあります。
相手が何の数字を出すかを読み切り、低い数字の手札で高い得点の札を獲得できればまさに気分は獲物をかっさらった「ハゲタカ」そのもの。
こちらも簡単なルールなので買ってすぐに遊べる、おすすめのボードゲームです。

『宝石の煌き』
『宝石の煌き』は、宝石商となり発展カードを購入し、資産を拡大することで名声を集めていくボードゲームです。
手番でできるのは
1.発展カードを買うのに必要な宝石トークンを2~3枚まで取る
2.コストを支払い発展カードを購入する
3.将来的に買いたい発展カードを予約して、黄金トークンを1つ得る
の3種類のうちどれかだけ、というシンプルなルールです。
その中で、発展カードなどについている名声ポイント(得点)を15点以上にすることが目的となります。
このゲームの面白い所は、すべての発展カードには宝石のアイコンが書かれている点でしょう。
獲得した発展カードは示された宝石1つ分を常に生産してくれるため、次以降に発展カードを獲得する際に役立ってくれるのです。
宝石は赤青緑白黒の5色に万能トークンとなる黄金の6種類あり、これらは発展カードのコストとして必要となります。
一方、宝石トークンは最大で10個までしか持てないにもかかわらず、10個以上の宝石を要求する高得点カードもあります。
つまり、最初はコストが安めの発展カードしか取れないのですが、カードを集めることでどんどん高い発展カードが買いやすくなるため、プレイしていて非常に気持ちいい、資産が拡大していくという体験ができます。
発展カードには様々な種類がありますが、どれもアイコンと数字だけで完結しているため、初見でもすぐプレイできますよ。

『ゲシェンク』
『ゲシェンク』は失点札を押し付け合う、ジレンマに満ちたボードゲームです。
内容物は3~35までの数字カード1枚ずつとチップのみというシンプルな小箱で、ルールも簡単なため、人さえ集まればいつでも遊べます。
『ゲシェンク』では各プレイヤーが手番で、公開された失点札に1得点相当のチップを支払いパスをするか、失点札を乗せられたチップごと引き取るかの2択を繰り返し、準備された失点札の山が尽きた時に得点が多かった(=失点が最も少なかった)プレイヤーが勝利します。
獲得した失点札は数字がそのまま失点となり、当然「30」以上の数字は誰もが引き取りたくないでしょう。
しかし、失点の計算にもルールがあり、連番の札がある場合、その連続した数字の内一番低い数字以外の失点は無視されるのです。
たとえば「30」と「31」の札がある時は失点は「61」ではなく「30」のみで、「31」は無視できます。
それどころかこの状態だと次の「32」も計算せずに済むため、チップ分得点が増えることもあります。
ただし、ゲーム開始時に全体の失点札から9枚をランダムに除外して非公開のまま箱にしまうルールがあるため、欲しい数字がそもそもゲームに登場しない可能性もあります。
みんなが取りたがらない高い失点札を取って、チップを集めるか、安全に失点を避けて低い数字を取り続けるか……。
チップが有限であることを考えたらジレンマに悩まされますが、自分の勝負勘が良い方向に出た時は気持ちよくてたまりません。
簡単に盛り上がれる上に持ち運びも簡単なため、旅行のお供などにもおすすめのボードゲームです。

『ペンギンパーティ』
『ペンギンパーティ』は、5色あるペンギンカードをピラミッド状に配置していき、手札を減らしていく簡単なボードゲームです。
ゲームのテイスト的には、ペンギンたちがパーティを行い、ピラミッドを作って遊んでいる、という一見平和なゲームなのですが、このゲームは非常にバイオレンスなゲームです。
というのも、ピラミッドの1段目(8枚)は好きな色のペンギンカードを出せるのですが、2段目以降は出す位置の足場となる左右のカードと同じ色しか出せません。
たとえば、黄色と青の間にペンギンを乗せたい場合はその2色のカードしか出せないのです。
そのため、ゲームが進んでいくと手札の出したい色がどこにも出せなくなってしまう……ということが起こり、ゲームから脱落せざるを得なくなります。
ちなみに乗せられなかったペンギンは海に落ちてシャチに食べられてしまうのだとか……。やはりバイオレンスなゲームですね(笑)
ルール自体は色や枚数からなる配置ルールと得点計算だけで、誰でも直感的に遊べるボードゲームです。
そのため、カードを広げられる場所さえあればいつでも遊べる簡単なおすすめボードゲームですよ。

『キングドミノ』
『キングドミノ』は簡単に遊べるタイル配置系ゲームの名作です。
プレイヤーは6種類ある地形タイルをルールに基づき自分の王国に配置していき、高得点を目指します。
タイルを配置するのは同じタイル配置ゲームの『カルカソンヌ』などとは異なり自分の王国上なので、計画性を持って自分の盤面を育てていきやすいです。
そのため、やや「箱庭感」があるかな、と感じる方もいるかもしれませんね。
でも、タイル取得のフェイズで他プレイヤーのタイル取得をカットするなど、他のプレイヤーの動向を気にする場面もきっちりあります。
配置ルールや得点ルールも複雑さはなく、誰でも理解できる簡単な内容で、ボードゲーム初心者でもある程度得点を伸ばしやすいため、おすすめのボードゲームです。

『海底探検』
『海底探検』はチキンレース系のボードゲームです。プレイヤーはサイコロを振って海底へ向かい深海のお宝を持って酸素がなくなる前に引き返します。
このゲームで特徴的なのは、プレイヤーたちが一つの空気タンクの酸素を共有しているところです。
そのため、自分は酸素を温存しながらプレイしているつもりでも、他プレイヤーがガンガン酸素を使っているとあっさり酸素がなくなり、海の藻屑となってしまいます。
また、お宝を取ると当然身体が重くなり、移動力の出目にもマイナス修正がかかるほか、持っている数だけ酸素も減っていくので、欲張りすぎるとろくな結果にはなりません。
全員が海の藻屑となり得点できない、というラウンドも多く、ワイワイ盛り上がることまちがいなし!
ルールも酸素の減り方さえ理解できれば後はサイコロを振って遺跡の宝を取るだけなので、簡単に初心者でも楽しめるおすすめの入門編ボードゲームといえるでしょう。

『ガンツ・シェーン・クレバー』シリーズ
『ガンツ・シェーン・クレバー』は6色あるサイコロを各ラウンドで獲得して、その色や出目に従って手元のシートに数字を書いたりチェックを入れたりしていく「紙ペンゲーム」と呼ばれるジャンルのボードゲームです。
手元のシートは5つのエリアに分かれており、それぞれの色ダイスに対応しています(6つ目の白ダイスは任意の色のダイスとして扱えます)。
各エリアごとに得点ルール(たとえばオレンジの色は記入した数値がそのまま得点になるといったルール)が決められており、ゲーム終了時にそれぞれのエリアの得点とシート上で獲得した「キツネ」のアイコンによる得点を合計して、スコアを競います。
シート内には得点だけでなく「ここに数字を書いたりチェックを入れたりしたら〇色のエリアに数字を書いていいよ」といったボーナスも用意されており、うまくいくと「ここにチェックを入れてそのボーナスでこっちに6を書いて、さらにそのボーナスであっちにチェックを入れて……」みたいなコンボを狙うこともできます。
ダイスの獲得数は親プレイヤーが3つ、子プレイヤーが1つと決まっているので獲得できるダイス数はほぼ固定ですが、このボーナスをうまく活用すればシートの多くの部分を埋めることができるため、出目だけでなく戦略も非常に重要となるボードゲームです。
手番の流れ自体は非常にシンプルですが、何度やっても考えることが多く、スコアという目に見えやすい指標が毎回出るため、こちらも初心者が簡単にボードゲームの奥深さを楽しみたい場合におすすめです。
日本語版がアークライト社から出ている『ガンツ・シェーン・クレバー』の他、子供用の『クレバー・キッズ』や最新作の『クレバー4エバー』といったシリーズ作もあり、1度『ガンツ・シェーン・クレバー』を知ればきっとこれらの派生作も遊びたくなるでしょう。

定期的にバネスト・ストアさんが仕入れて和訳ルールをつけたものを販売してくれているので、1作目をやって気に入ったら要チェックだ。
家族や友人を誘って手軽にボードゲームを遊ぼう
本記事では初心者にも簡単に遊べるルールでルールブック以外の文章をほぼ読む必要がないおすすめボードゲームを9個紹介してきました。
「ボードゲームというと楽しそうだけど難しそう……」という印象が少しは解消されましたでしょうか。
『レキシオ』のように牌を使うなど、内容物が豪華なゲームは子供にも親しまれやすいため、家族で少し遊ぶのにも最適です。
牌を使ったおすすめのボードゲームは下記記事をご参照ください!
レキシオとともに楽しめる、家族で遊ぶ牌系ボードゲームたち | Lexio store (lexio-japan.com)
さあ、皆さんも手軽に気軽にボードゲームを楽しみましょう!
最後までお読みくださりありがとうございました!
LexioNeo-レキシオネオ
商品紹介
Lexioplus-レキシオプラス(日本語マニュアル付き)
商品紹介
Lexioロゴ入り特製プレイマット
商品紹介
関連情報